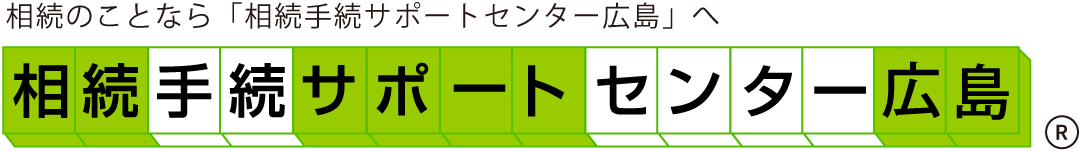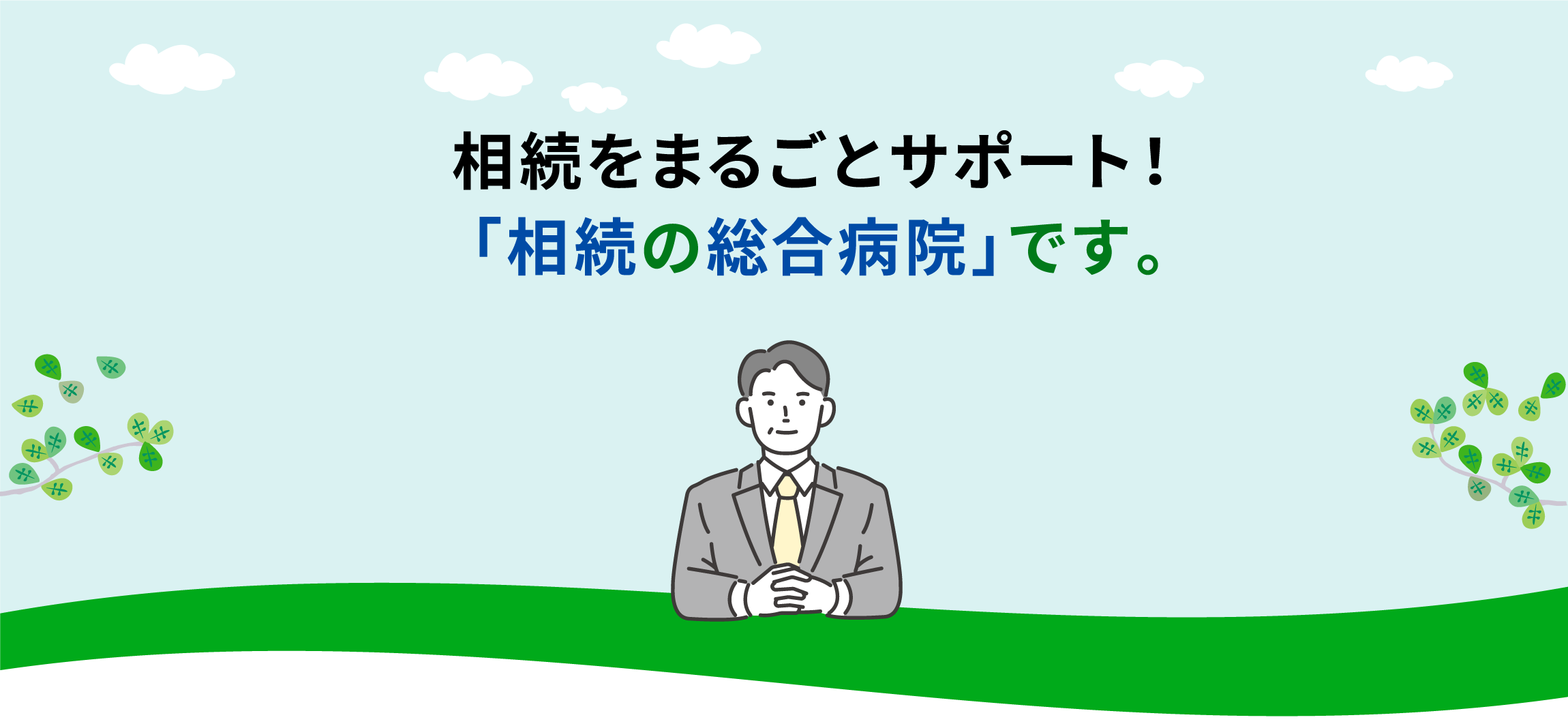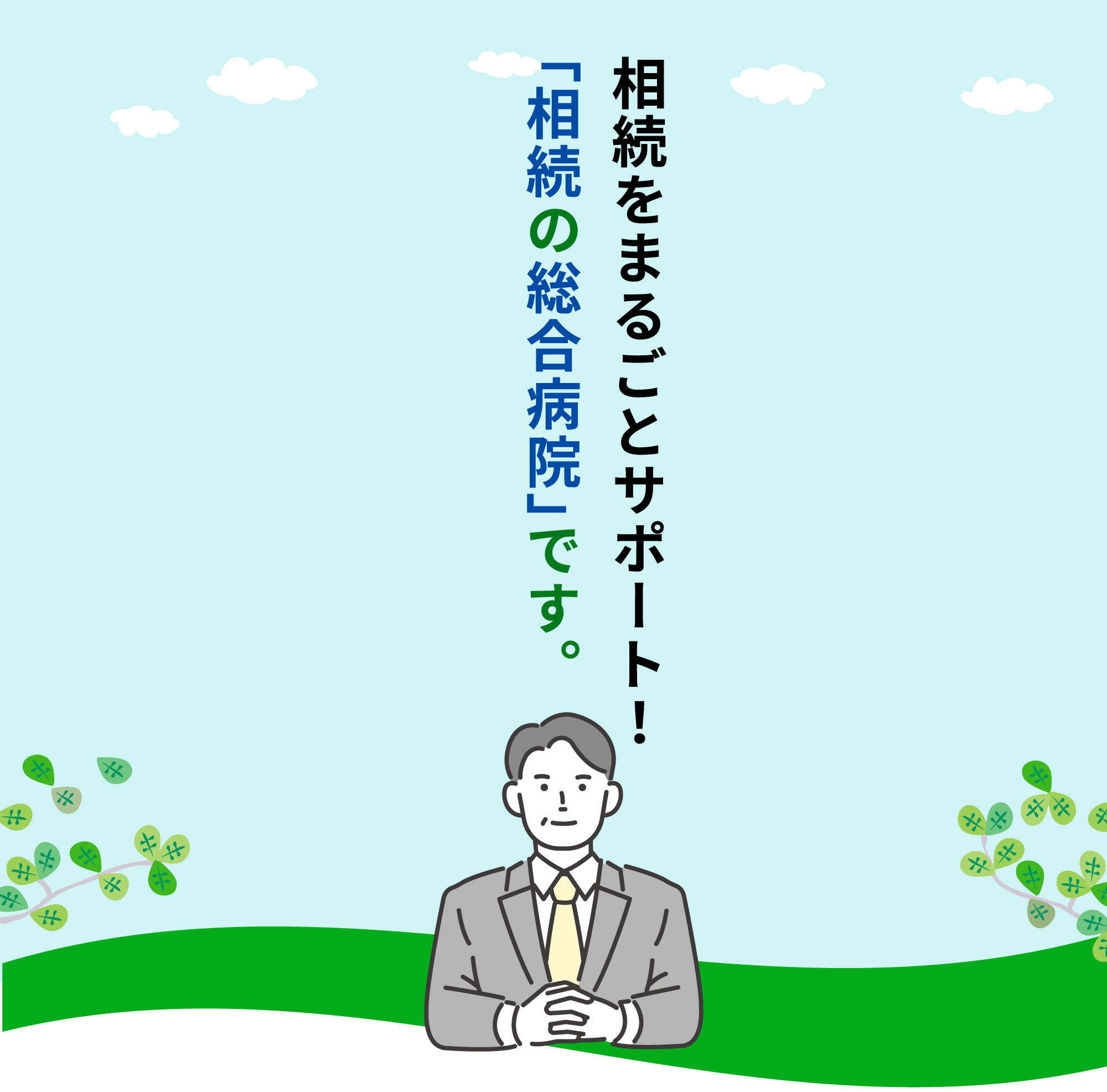相続の専門家が
ワンストップで解決!
相続手続サポートセンター広島は、「トラブルにならない上手な相続対策」から、煩雑な相続手続の代行にいたるまで、相続に関するサポートをトータルでご提供する、言わば「相続の総合病院」です。
実績豊かなスタッフが、安心と効率の良い相続手続き全般について、心をこめてお手伝いいたします。
まずは、無料相談をご利用ください。
 複雑な相続手続きを
複雑な相続手続きをまるごとサポート!
相続の専門家集団による窓口の一本化で、時間の短縮とコスト削減につながります。
 専門家集団が
専門家集団がワンストップ対応
司法書士・弁護士・税理士・行政書士など各専門家と連携。
ワンストップでサポートします。
 相続登記
相続登記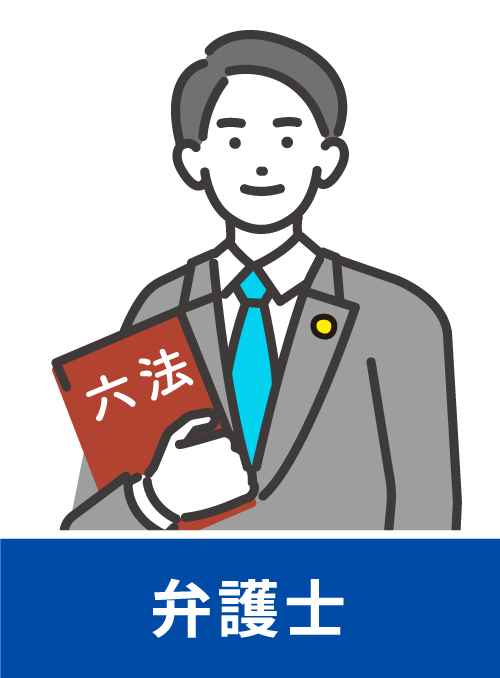 調停・裁判
調停・裁判 税務申告
税務申告 自動車の名義変更
自動車の名義変更 土地・建物の測量
土地・建物の測量 不動産価値の鑑定
不動産価値の鑑定生前の相続対策
相続手続きは、どのご家庭にも必ず関わってくるものです。
「トラブルにならない上手な相続対策と準備」をご提案します。
- 遺言書の作成
-

- 家族信託
-

- 「生前の相続対策」 サポートのながれと料金について
- 詳しく見る

- 相続手続き 相続登記が義務化されました
- 家族信託 家族信託で認知症の備えを
- 生前対策 内縁の妻 または 夫などに法定相続分はあるか
- 遺言書 困った遺言書
- 相続手続き 遺産整理業務のご紹介